椎名誠といえば、中学校の国語の教科書にのっている「アイスプラネット」などで有名な作家だ。個人的にも、椎名誠はこの中学校のときに読んだ話で初めて知ったので、それを真っ先に思い出してしまう。同時に、世界の辺境に旅をして写真を撮っている作家であるということも当時知って、変わった面白い作家がいるんだなと思ったことも覚えている。
しかし、その椎名誠がSF作品を書いているということは、大学に入ってからSF研の後輩に勧められて始めて知った。それも、本格的な終末SFで、冒険ものの作品があるらしい。後輩が勧めてくれたもののなかでも、一番薄くて読みやすそうだった『武装島田倉庫』を読んでみたのだけど、かなり面白かった。終末世界を描いた作品だが、その世界観や語り方が魅力的な作品であり、気に入ってしまった。
物語は島田倉庫という倉庫に男が就職するところから始める。男は、この倉庫に仲間の男たちと寝泊りすることになり、倉庫に搬送されてくる荷物をしまったり、荷出しをしたりといった仕事を覚えていく。この時点ではまだ世界観が分からないのだけど、倉庫にカミツキウオ1なる異常な生物が運ばれてくること、倉庫に物資を運んでくる運送屋たちが、外で略奪団に襲われた話を持ち込んでくることから、物騒な荒廃した世界が広がっているらしいことが分かってくる。そのうち、ついに白拍子という略奪団が倉庫を襲い始めたという噂が島田倉庫にも届く。倉庫の人々は、彼らに対抗するため、銃をとって武装し始める(不思議なタイトルだなと思ったけれど、だから「武装島田倉庫」なのだ)。
このような短編が、表題作に加えて「泥濘湾連船」「総崩川脱出期」など、7作収められている。それぞれの短編では、登場人物も舞台も異なるが、全て同一の、近未来の戦争のあとに文明が崩壊した世界におけるドラマが描かれる。各短編において重なる描写から、荒廃した世界の全貌が明らかになっていくところが、この構成を活かした面白みとなっている。例えば、作品には様々な独特の地名(阿古張湾、吊目温泉など)が登場するのだが、これらの地名は複数の話に登場するので、読んでいるうちに地名がつながって世界の地図が広がっていく感覚が楽しい。物語は硬質な筆致で淡々と描かれており、人間的なドラマというよりも、SF的な世界が明らかになっていく過程が私には面白かった(特別な立場の人間からでなく、普通の労働者の視点から描かれているのもこの作品もポイントだろう)。そういった構成上の特徴から、あまり世界観を説明しすぎては初読の楽しみを削ぐかもしれないが、魅力的な世界観が伝わるように説明してみると、泥と油に覆われた海、異常発達した生物、組織略奪団や北政府との闘い、SF的メカ・乗り物といったところがキーワードがあげられる。
まず、泥と油に覆われた海だが、この世界は海が油と泥に覆われており、人々は油泥まみれの海のまわりで暮らしている。この作品で描かれる文明崩壊後の世界は、決して美しい終末世界ではなく、作品に登場する尻拭湖、小便桟橋、南汗布市といった固有名詞からイメージされるような、じめじめした汚らしい世界として描かれていているのが特徴といえる。
収録2つ目の「泥濘湾連絡船」は、油泥で覆われた湾にかかっていた橋が落ちてしまったので、渡し船を通して儲けようとする男たちの話で、カミツキウオなどの異常な生物が潜んでいるか分からない泥濘湾を、ザンバニ船で航路を開拓していくところは、冒険小説的のような面白さがある。
椎名誠のSFには、不思議な生物が出てくるのが特徴みたいだが(ほかの作品は未読だが)、『武装島田倉庫』にも異常発達した生物がたくさん登場する。カミツキウオや、職種口を伸ばして人を飲み込む植物の壺口など、それらはこの世界で暮らす人々の脅威となっている。そのほかにも、ときに名前だけの言及として様々な生物が現れ、これらの固有名詞の数々が未知の世界を彩っている(地名や人名もそうだが、なんといっても固有名詞からの世界観の見し方が特徴的な小説である)。
この世界がどうして崩壊してしまったのかは詳しく語られないが、北政府なるものが関連していたらしいこと示唆されている。そして、いまも住民たちは北政府との間で緊張状態にある。3作目「総崩川脱出記」は北政府から逃れながらの旅が描かれ、5作目「肋堰夜襲作戦」では北政府への夜襲が描かれている2。
4作目「耳切団潜伏峠」は、物資の輸送のために、組織略奪団の潜む廃道を装甲貨物車で越えていく男達二人の話だ。その運転手の助手になった少年が主役だが、装甲車自体がもうひとつの主役ともいえる。十六輪の巨大な装甲貨物車は、蔦だらけの廃道を乗り越え、障害物を破壊して進む。6作目「カミツキウオ白浜騒動」には、カニムカデなる九足歩行の乗り物が登場する。この乗り物に少年が乗り込んで、表面が油で覆われた海の底の沈没船から物資を運び出したりするのだが、ロボットアニメを思わせるような話でわくわくさせられる。このように戦争で都市が破壊されたと後とはいえ、戦時中に使われたのであろうガジェットも登場するのも萌えポイントだ。
危険生物、冒険、乗り物など、男の子がわくわくせずにはいられない話が多い3。どれもSFらしいSFにはでてくるものだし、それをいったら男の子の好きなモチーフだらけなのはSF自体そうだろうなどといわれればそうなのだけど、『武装島田倉庫』はとくに少年心をくすぐる要素があるように思う。ごく普通の男たちが、社会という上からのルールに従うのではなくて、みずからの才覚を頼りに生きのびかたを開拓しながら生きている感じが、子供たちが自分たちのルールのなかで秘密基地をつくったりして遊んでいる感じと近いからなのかもしれない。あるいは作者がそういった感覚を忘れずに持っている人だからなのか。読んで、童心に返らされるような感覚があったのはそのためなのかだろうか。
少年にとっては、泥だらけのなかでも自分が自分の生を主導しながら生きていることが楽しい。それと同じで、『武装島田倉庫』は泥と油まみれで、生物は以上発達し、北政府や略奪団の存在で緊張状態にあるような絶望的な世界でありながら、『武装島田倉庫』の人々は決して暗くはない。彼らはそんな過酷な世界のなかで、生き延びるための生活を実にしたたかに送っている。「泥濘湾連絡船」では、町のひとったちが渡し舟ができたことを聞いて、興味を持って集まってくる(ここらへんのやりとりなどは、なんだか落語に出てくる町人たちの会話を感じさせて特に明るい4)。「耳切団潜伏峠」は装甲貨物車の運転にあこがれていて、運転手の助手になる機会を得たことを喜ぶ。「カミツキウオ白浜騒動」では仲間たちと獲物をえた喜びが描かれる。いずれの話も人々が徹底的に災難に翻弄されながらも、最後には光を感じさせるようなタッチで物語がとじられる。最後の収録話の「海帆島田倉庫」のラストは特に印象的だ。
SF的な説明はかなり少なながらも、非常にSF的な世界、それもどこかアジア的なポストアポカリプス を独特の語彙と語り口で描き、その世界のおける男達のサバイバル(生き延びるための生活を含めて)を独特なリアリティーで描く小説、なかなか他にはみたことのない話でとても良かった。
面白かったので、他の椎名SFも読んでみたいと思う。
- 魚偏に乱、魚偏に齒の二文字でカミツキウオと読む。入力できないけれど、「魚乱 魚齒」という感じ ↩︎
- 椎名誠はほかにも北政府が登場するSFを書いており、「北政府シリーズ」と呼ばれることがある) ↩︎
- もちろん、男の子だけでなくてアクティブな女の子にとっても楽しい小説だとは思うが、実際登場人物は男ばかりで、いってみれば非常に男臭い小説という部分もある。変にわざとらしいヒロインが出てこないのもまた、過酷な世界で生き延びる男達のリアリティーになっていると思う。 ↩︎
- 登場人物の名前が古風で、江戸っ子のような口調?というところからの連想もしれないが。とにかく、読めば伝わると思うけれどこの話は特に登場人物たちのやりとりに、なんというか昭和の下町のような雰囲気がある。「泥濘湾連絡船」が一番下町っぽいが、「総崩川脱出記」は一つの群族の話だし、「カミツキウオ白浜騒動」も漁師たちのムラ的な共同体を中心とする話だ。文明が崩壊して都市が存続できなくなったので、ムラ的な共同体のなかでひとびとが生きているということなのだろう(風の谷的なスタイル)。本作品は文庫本のあらすじ紹介にもノスタルジックという言葉で紹介されているけれど、そういった懐かしい共同体の風景が見え隠れするところが、近未来を描きながらもノスタルジックに感じるといわれるポイントなのだと思う。 ↩︎
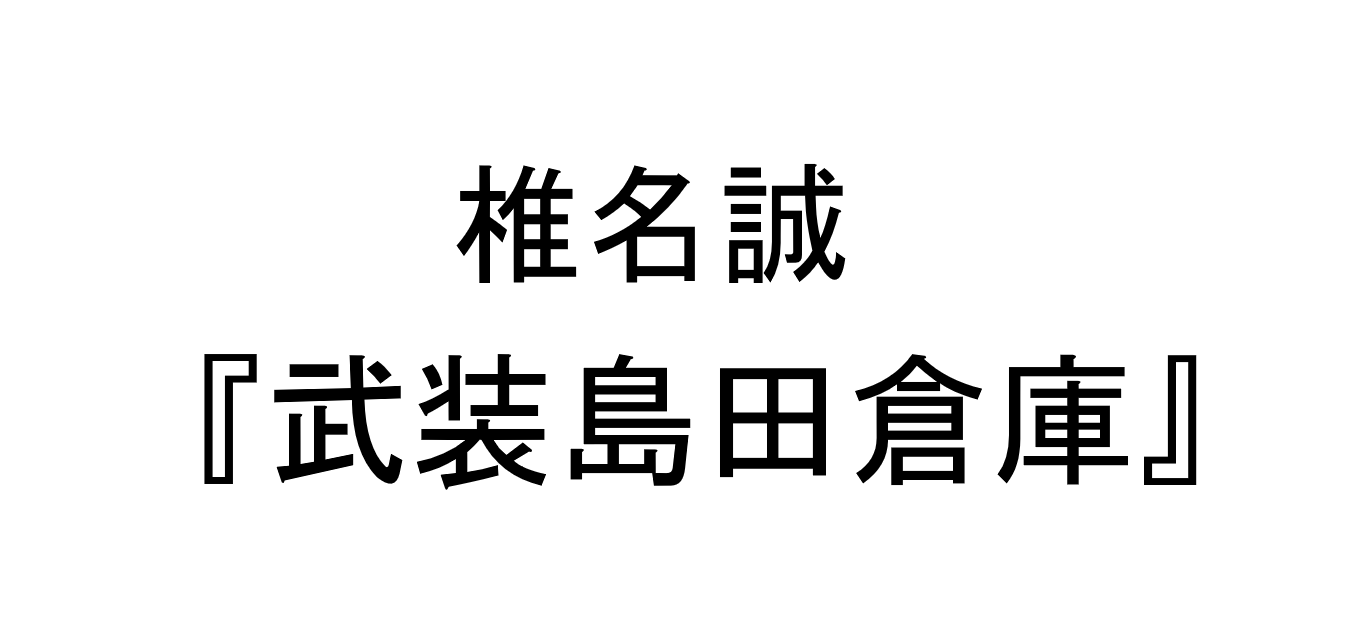
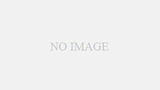

コメント