●『西瓜糖の日々』の透明な世界
『西瓜糖の日々』(藤本和子訳)は、アメリカの詩人・作家であるリチャード・ブローティガンが1964年に書き上げた、短く断片的な章からなる詩的幻想小説である。
西瓜糖(Watermelon sugar)というのは、この小説の世界で、西瓜から作られる(架空の)砂糖のこと。西瓜糖でさまざまなものができた架空の世界の住人が、私たちに向けて西瓜糖の世界を伝えようと書かれた文章が、本書という構成になっている。
いま、こうしてわたしの生活が西瓜糖の世界で過ぎていくように、かつても人々は西瓜糖の世界でいろいろなことをしたのだった。あなたにそのことを話してあげよう。わたしはここにいて、あなたは遠くにいるのだから。
『西瓜糖の日々』(p.9)
本の書き手は「きまった名前を持たない人間のひとり」で、友人のチャーリーに進められて、この世界で24冊目の本を書くことにする。
この世界では、橋や家は西瓜糖でできていて、曜日によって違った色の太陽がのぼる。いたるところに人や野菜の彫刻が立ち、無数に流れる川の底には、ガラスの棺が沈んで死者たちが埋葬され、夜には光を放って川底を照らす。私は小さな小屋に住んでいて、仲間たちの集まるアイデス(ideath)という場所で食事をとる。
登場人物たちの会話は童話的で、夕食のこと、職場で見つけた蝙蝠のこと、わたしの書いている本のことが語られる。
静かで、単純で、とても変わっているがなぜか懐かしい、そんな不思議な世界。しかし、単に現実を違う世界を描いた幻想小説と紹介したところで、この世界の手触りは伝わらないだろう。
この小説には、読んでいて心が透明になっていくような、不思議で、こういってよければ不気味なまでの穏やかさがある。この西瓜糖の世界で描かれるのは、かぎりなく死にも近いほどの穏やかさなのだ。
訳者の藤本和子さんもあとがきで書いている、「過度な感じの不在」というのが、この世界の手触りの本質だろう。
あらゆるものや情報であふれているこっちの世界の住人である私たちからみると、西瓜糖の世界は驚くほど空虚にみえる。例えば、本はいままで23冊しか書かれたことがなく、私が家具や文房具のほかに小屋もっているものは、たったの九つだけである。
いろいろな物をしまっておく大箱のところへ行って、花の種子を取り出そうとすると、何もかもごちゃごちゃになって入っているのに私は気がついたので、種子を蒔く前に、まず物を元通りにした整頓した。
わたしは、だいたい九つのものをもっている。子供のボール(どの子供のだかは忘れてしまった)、九年前にフレッドがくれた贈り物、天気に関するわたしの作文、数字のかたちをしたもの(1から24まで)、着替え用のつなぎ服一着、青い金属片ひとつ、<忘れられた世界>にあった物、洗わなければいけない髪の毛ひと房。
『西瓜糖の日々』(P.86)
一方、この世界のはずれにある<忘れられた世界>という場所には、用途のわからない様々なものがどこまでも積み重なっている。アイデスの過剰なものが欠如した世界に対して、<忘れられた世界は>はまさしくわれわれの住む現実世界のように、過剰なものの象徴として対比づけられている。
物語の中盤では、かつて私の両親をたべてしまった人間と同じ言葉を話す虎たちのこと、アイデスのもとを離れ<忘れられた世界>に取りつかれてしまったインボイルたちのこと、わたしの恋人だったマーガレットとの軋轢が描かれる。
西瓜糖の世界は決して、童話的な優しい世界というわけではない。暴力や不条理や対立についても、西瓜糖を語るのと同様の穏やかで静かなトーンで語られる。
物語序盤で語られるアイデスの過剰なまでの穏やかさは、中盤で語られる残酷さとの微妙な均衡のもとで存在している。その危うさがまた魅力なのである。
アイデスでは、どこか脆いような、微妙な感じの平衡が保たれている。それはわたしたちの気に入っている。
『西瓜糖の日々』(P.9)
●ブローティガンの詩世界
このような穏やかな西瓜糖世界の手触りは、ひとつにはブローティガンの、どこか脆さを秘めたような詩的な文章によるものだと思う。本書はひとつの章が1~5ページ程度の短い文章になっていて、それぞれが独立した詩のようになっている。
決して難しい言葉は使っていないのに、ゆっくりと咀嚼してこの世界の時間の流れにひきずりこむような、速読を許さない文章。彼の詩はひとつひとつが断片的でとらえどころがなく、余韻を大事にしているように感じられる。
ブローティガンは、日本の俳句を愛した詩人だった。彼がつくる詩には、決して強い言葉ですべてを語ろうとはせず、小声でそっとそのとき感情の雰囲気のようなものを囁くような、俳句に似た趣がある。まさしく「西瓜糖」という言葉のように、小さく脆くとらえどころがないが、甘い芳香を持っているのが彼の詩の特徴なのだ。
ゆっくりきみをその気にさせよう、
まるで夢のなかでピクニックを
しているような気持ちに。
蟻なんていないよ。
雨なんて降らないさ。『ここに素敵なものがある』(中上哲夫訳)
例えば、ブローでぃガンの詩集のなかに収められたこの詩で描かれる「夢のなかのピクニック」は、『西瓜糖の世界』の過剰なものが不足した世界に共鳴するようだ。このようなあらゆる過剰さと縁のない、透明な優しさに満ちた世界が、彼の詩世界を特徴づけるひとつの方向性のように思える。
だからこそ、現実世界の過剰さに疲れを感じる繊細な人間にとっては、ブローティガンの作品が癒しとなるのだろう。
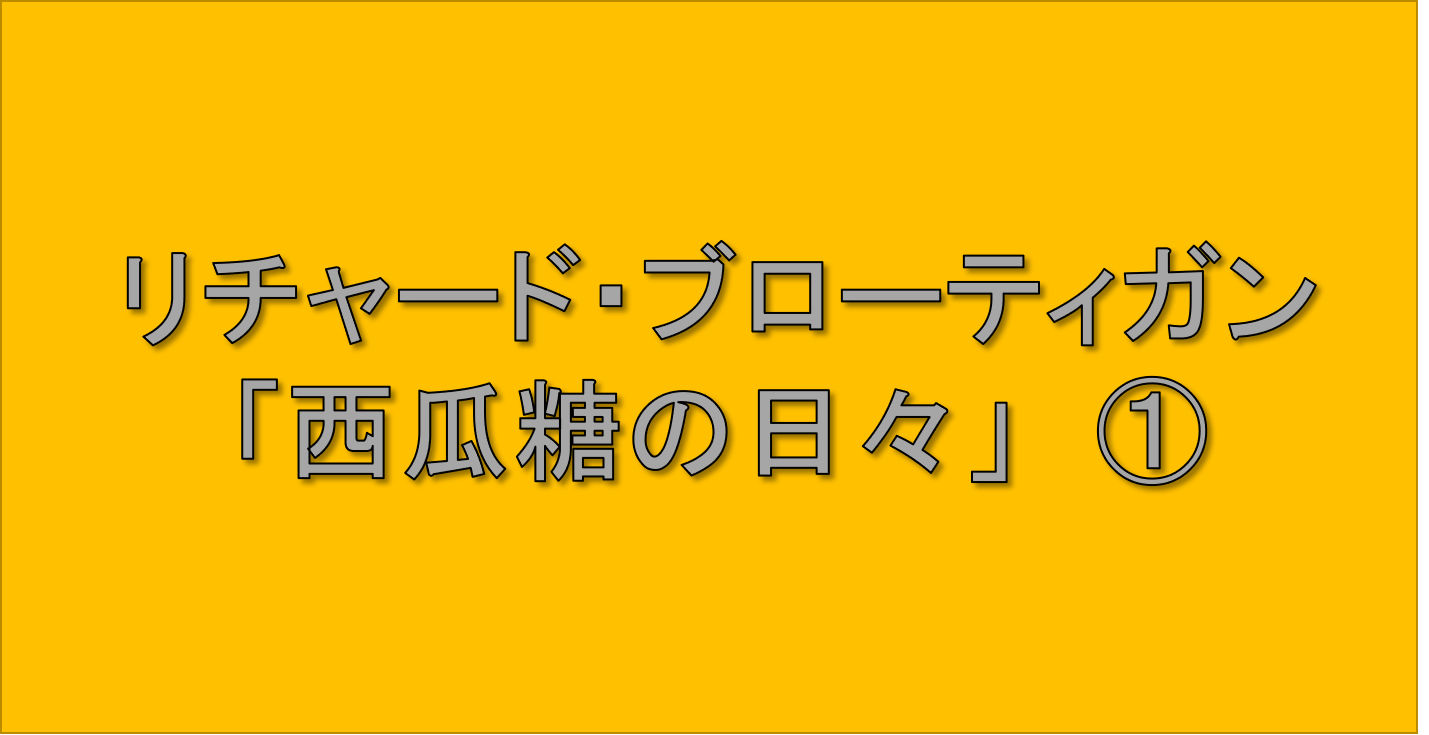


コメント