前回の記事で、リチャード・ブローティガンの、西瓜糖でできた別世界のことを書いた詩的幻想小説『西瓜糖の日々』を紹介した。西瓜糖の世界は、我々の世界とは別の秩序で作られる風変りな世界だが、優しくてどこか懐かしい。その本質が、「過度な感じの欠如」にあることをみてきた。
リチャード・ブローティガンはビートジェネレーションの代表的作家であり、ヒッピー達は支持されていたことが知られている。確かに本作の物質的な豊かさへの反発はビートジェネレーション的だし、アイデスはヒッピー的のコミューンに通ずるものかもしれない。
しかし、本作が書かれたのは1964年のことであり、当時はヒッピーが登場しておらず、のちにヒッピー文化の偶像として祭り上げられる『アメリカの鱒釣り』の刊行もされていなかったことが、柴田元幸の解説で書いている。
実際に私自身も60年代のヒッピー文化には詳しくないので、それと重ねた読みはできなかったのだが、柴田元幸は「六〇年代の高揚と挫折に対する屈折する感情的反応が過去になりつつあるいまこそ、六〇年代とは切り離して、ブローティガンをブローティガンとして読む好機かもしれない」と述べている。
では、ブローティガンを特定の時代的文脈から切り離した、アメリカの一詩人・作家としてみたとき、彼の描いた過度に欠落した懐かしく優しい世界は何なのだろう。それは60年代の世代的な空気を超越して、アメリカ文化全体のひとつの心象風景なのではないか、というような気がする。
西瓜糖の「何かが欠けたどこでもない世界」に触れたとき、なんとなく連想したのは、最近英語圏を中心にしてインターネットで流行している、ドッリームコア(dreamcore)の世界観であった。このドリームコアや、関連するインターネット美学(liminal space, wired coreなど)は、西瓜糖の世界と通底する美学を持つように思えるの。『西瓜糖の日々』の話からはずれるが、ドリームコアについて紹介してみたい。
●“どこでもない場所”へのノスタルジー。dreamcore的なもの
ドリームコアは2019年~2020年ごろから(日本でやや遅れて2021年ごろから)流行したもので、夢のなかのような、どこか不気味で違和感があるがノスタルジックな感覚を催させるような画像や音楽、動画などを総合した美学のことを指している。具体的なモチーフとしては以下のように、住宅街などの無人の空間、風船やボールなどのカラフルで幼児期を思わせるアイテム、青空と建物を組み合わせたシュールレリスムのような非現実的な景色、古いインターネットやゲーム機のバーチャル空間などがある。それらのモチーフを使って、夢の中らしい、行ったこともないのに知っているような景色が表現されている。


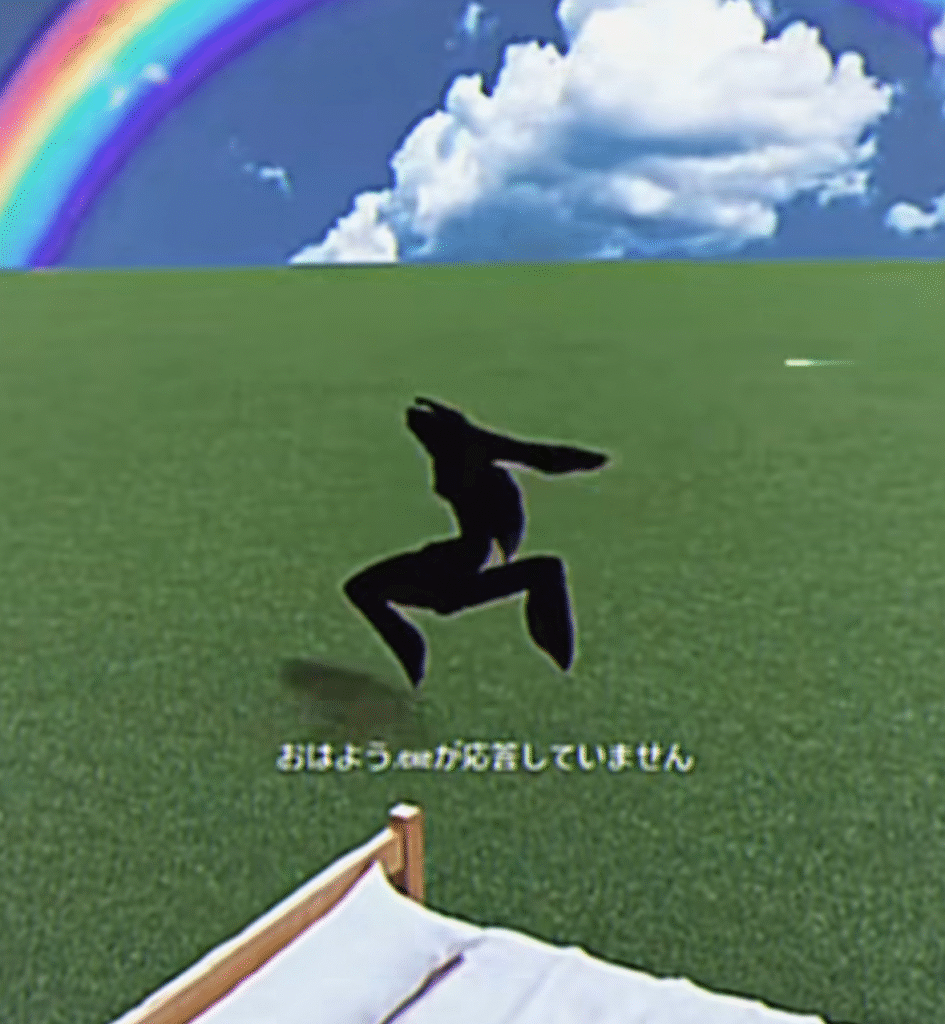
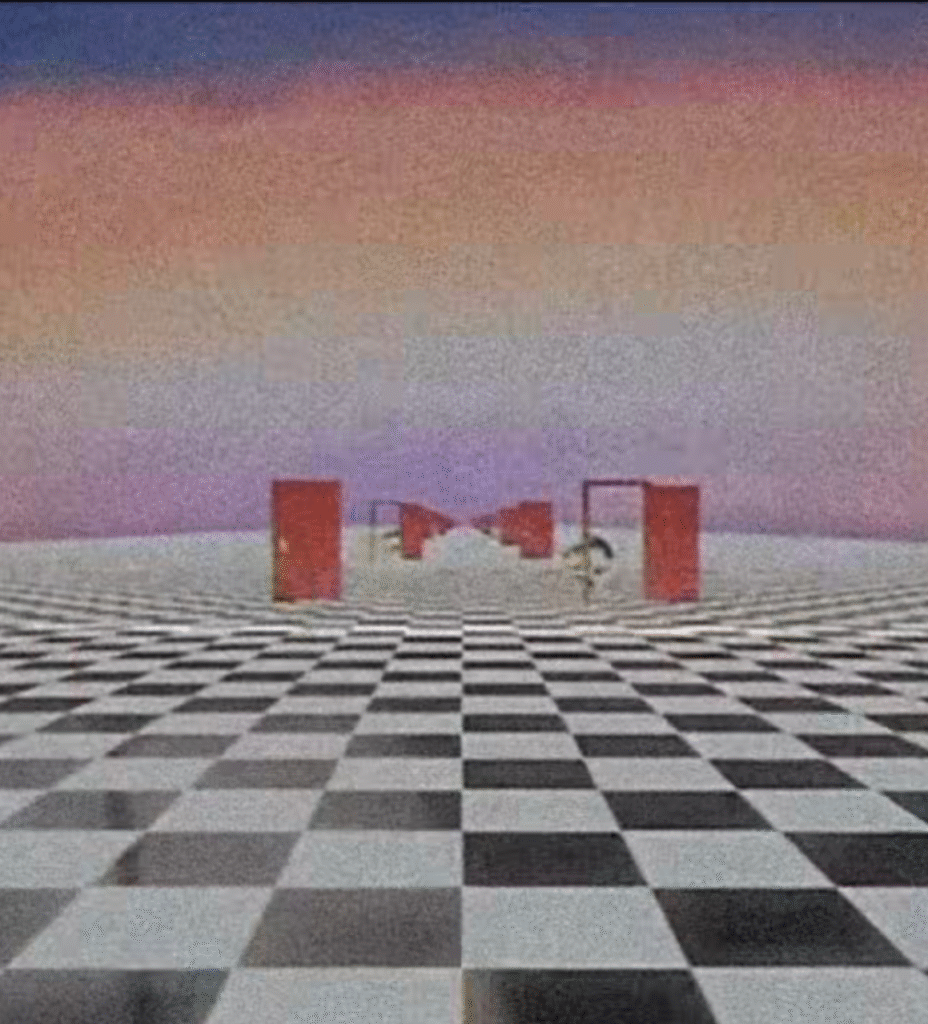
ドリームコアに先行して流行していたリミナルスペース(liminal space)は、誰もいないデパートやオフィスの廊下、プールなど、公共施設の無人の空間に対して感じる、不気味さと懐かしさの混じった感覚を扱った美学だった1。それら、リミナルスペースで扱われる景色の特徴は、具体的な場所の記憶を持たない「どこでもない場所」であるという点である。ショッピングモールや公共住宅地などの、歴史性をもたない、どの町にも同じようなものがあるといった類の空間。その種の大量消費社会的な、「見たことはあるけれどどこかは分からない場所」への郷愁が、中心的なテーマになっていた。
ドリームコアでは、リミナルスペースと同様なモチーフは引き継がれるが、もはや現実の空間を超えた超現実な景色が多く扱われる。リミナルスペースでは現実の空間のなかの、どこでもない一角であったのに対して、ドリームコアでは幼児期の記憶の中の景色や夢の中の景色といった精神的な景色、古いテレビ番組のなかのようなメディアのなかの景色、そして古いゲームやCGのようなバーチャルな景色へと発展している2。そしてこれらも、具体的な場所の記憶を持たない「どこでもない場所」という点で共通しているのだ。
この、はじめは現実の空間への美学だった、「どこでもない場所」へのノスタルジーが、サイバーな空間にまで発展するのは、なかなか面白いことだと思う(frutiger aeroなどの別の美学にもこの兆候はみられる)。そして、ここまで「どこでもない空虚な空間」に対しての懐かしさが、共通の感覚として受け取られることはアメリカの美学の特徴的な点と思われる。
もちろん日本人にとってもこの感覚はよくわかるのだけど、日本的なノスタルジーというと、まず思いつくのは神社の境内とか、夕暮れの田舎道とか、古民家やレトロな商店街など、歴史的な記憶や季節性に基づいたモチーフのほうが強い。ヨーロッパでもおそらく、お城や祭りや古民家などの歴史性のあるノスタルジーが大きいだろう。アメリカの場合も「古きよきアメリカ」へのノスタルジーという、伝統的な景色に対するノスタルジーの方向性はあるにしても、やはりドリームコア的な「どこでもない場所」への郷愁への共感は大きいように思う。日本やヨーロッパのような規模の歴史を持たない国であるだけに、記号的・仮想的空間に郷愁を求めやすいという傾向がやはりあるだろう。
そしてまた、こうしたモチーフはアメリカの文学や映像作品でモチーフとしてよくあらわれるように思うのだ3。(例えば、キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」や「シャイニング」にはリミナルスペース的なモチーフが現れる。リミナルスペース・ドリームコアコア的作品の具体的な例についても、追求していくと面白いと思っている)
「西瓜糖の世界」は、ドリームコアほど不気味な感じはしない、優しい童話的な世界である。未読の人に、両者が似ているというと先入観を与えることになってよくないかもしれない。しかし、西瓜糖の世界に感じられる「どこでもない場所」へのなつかしさが、かたちを変えて現代のインターネットでも繰り返されているというのは面白い点であり、その意味で『西瓜糖の日々』には古びない面白さがあるといえると思う。
巨大な大陸の荒野に街をつくり、そのかわりに歴史性など欠けたものを抱えざるを得ないというアメリカ的な孤独が、詩人の繊細で優しい精神世界に反映されて生まれたのが、『西瓜糖の日々』のようなブローディガン作品なのではないかと、やや壮大な妄想を広げた感想であった。
- 最近、リミナルスペースについて論じた本が出たようで、未読だが大変気になっている。『リミナルスペース 新しい恐怖の美学』(Alt236著、佐野ゆか翻訳) ↩︎
- 現実の場所としてのリミナルスペースと、バーチャルな空間にまたがる象徴的なイメージが、windowsXPの壁紙の草原である。この草原のイメージは、僕にとっては不思議と「西瓜糖の世界」に重なる。これは僕の妄想なのだけど、「西瓜糖の世界」がもしあるとすれば、この低画質な草原の丘の向こう側に、この世界がひっそりと存在しているように感じられるのだ。 ↩︎
- 僕の読書量が少ないだけかもしれないが、日本の作家でこういうドリームコア的、あるいは西瓜糖の世界的な美学で書かれた作品は少ないように思われる。例外は米文学の影響を強くうけている村上春樹で、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の「世界の終わり」は、西瓜糖の世界と近い感触があったように思う(読んだのが昔でうろ覚え)
また、「8番出口」はリミナルスペースをモチーフにした日本のゲーム(及び映画)だが、「異界訪問譚」的な日本人好みのモチーフも入っているな、など思ったり。(一方、フィンランドのクリエーターの作った「pools」というゲームはより原理主義的な?リミナルスペースを味わえるゲームだった) ↩︎

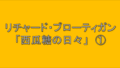
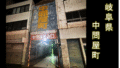
コメント